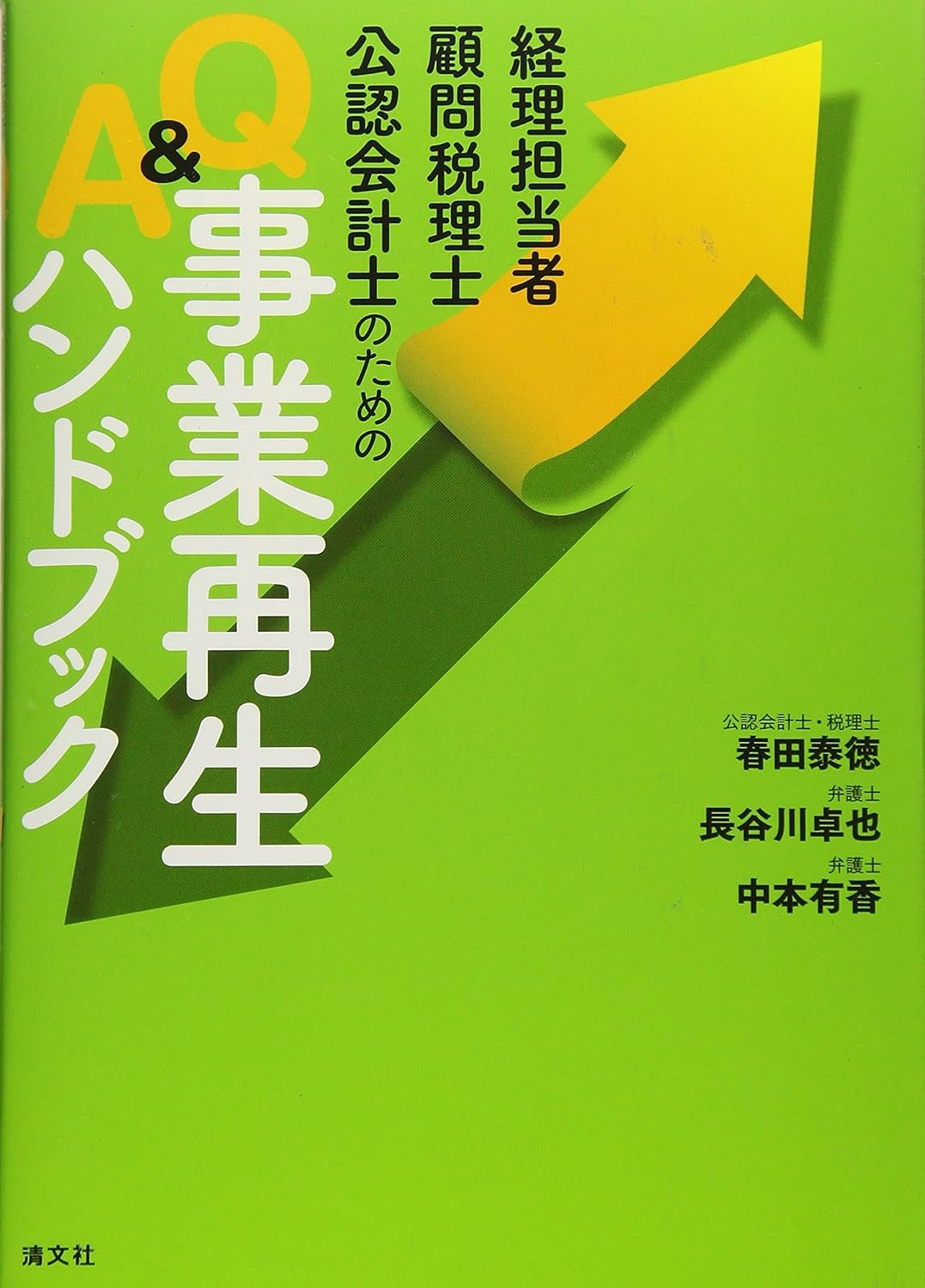こんにちは。本日はこちらの記事を論説したいと思います。
Yahooニュース:曙ブレーキ、28年3月期に営業益6割増…〝赤字体質〟事業改善なる …
事業再生の成功事例: 曙ブレーキ工業の挑戦
事業再生とは、経営が困難に陥った企業が立て直しを図るための一連のプロセスです。曙ブレーキ工業は、その典型的な成功例として挙げられます。2019年1月に事業再生ADR(Alternative Dispute Resolution、裁判外紛争解決手続き)制度を利用し、経営再建に着手しました。その結果、2024年6月には事業再生計画の実行が完了し、収益性の改善と基盤の再構築を目的とした中期経営計画を発表するに至りました。
事業再生とは何か?曙ブレーキ工業の取り組みを解説
曙ブレーキ工業の事業再生は、経営上の課題であった「赤字体質」の改善に成功した点が注目されます。事業再生ADRは法的な手続きによらず、専門家の助言を得て経営を立て直す仕組みです。この手続きを通じて、曙ブレーキは収益性の低かった既存事業を見直し、新たな成長戦略を策定。特に四輪車事業では、高付加価値補修品のシェア拡大に注力し、黒字化を目指しています。
曙ブレーキの中期経営計画とは:2028年3月期の目標を紐解く
曙ブレーキは、2028年3月期に営業利益で約6割増の80億円を目指す中期経営計画を立てています。これは、既存事業の収益性を高めるとともに、新たな技術開発や市場展開を通じて基盤を強化することを意味します。具体的には、鉄道事業での油圧ブレーキの拡販や、欧州での新しい貨物向けビジネスの開始が計画されており、これらが収益へ貢献することが期待されています。
事業再生ADR制度の活用とその成果
事業再生ADR制度を活用した結果、曙ブレーキ工業は経営再建を成功させました。この制度により提供される第三者の専門家のアドバイスは、経営状況の客観的な分析と、実現可能な改善策の提案に役立ちました。そして、経営の見直しにより、経常損益が改善されるとともに、資金繰りの健全化が進んだのです。
事業再生への具体的なステップ
収益性改善:曙ブレーキの四輪車事業の転換戦略
「赤字体質」からの脱却を目指すため、曙ブレーキは四輪車事業において収益性の改善に注力しました。具体的には、製品の高付加価値化と生産効率の向上を図り、コスト削減と収益増につなげています。また、市販向け補修品のシェアをさらに拡大することで、利益率の向上を目指しています。
新たな市場への挑戦:曙ブレーキの鉄道事業と海外展開
曙ブレーキは、鉄道事業を新たな成長の柱と見込み、油圧ブレーキの拡販を図っています。また、欧州での新規ビジネスやインド市場への合弁企業設立など、積極的な海外展開により、グローバルな市場へと事業を広げているのが特徴です。新技術の開発や新商品の投入も、今後の成長に向けた戦略の一環です。
研究開発への投資:将来の成長を見据えた取り組み
長期的な成長を目指す上で、研究開発への投資は不可欠です。曙ブレーキは、将来に向けた設備投資として220億円を計画しており、安全や品質に関わる分野への重点投資を行っています。また、売上高の4~5%を研究開発費に充てることで、技術革新に対応した新製品開発を継続的に行い、持続可能な企業成長を目指しています。
経営者が学ぶべき事業再生のポイント
事業再生計画の策定と実行の重要性
事業再生計画の策定と実行は、経営再建の核となります。曙ブレーキ工業の事例から学べることは、明確な目標設定と具体的なアクションプランが成功への鍵であるという点です。経営者は、現状の課題を正確に把握し、適切な改善策を策定する必要があります。
経営課題の特定と解決への取り組み
経営課題の特定と解決への取り組みは、事業再生のプロセスにおいて重要なステップです。曙ブレーキは、経営課題であった米国事業の黒字化に注力し、長期的な視野に立った経営戦略を構築しました。経営者は、このように具体的な課題に対し、戦略的なアプローチを行う必要があります。
長期的視点に立った経営戦略の構築
事業再生においては、短期的な利益追求だけでなく、長期的な視点を持つことが成功には不可欠です。曙ブレーキ工業は、次期中計に向けた新技術の開発や新市場への挑戦により、未来の成長への投資を行っています。経営者は、このように将来を見据えた経営戦略を構築し、持続可能な成長を目指すべきです。